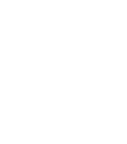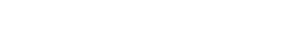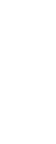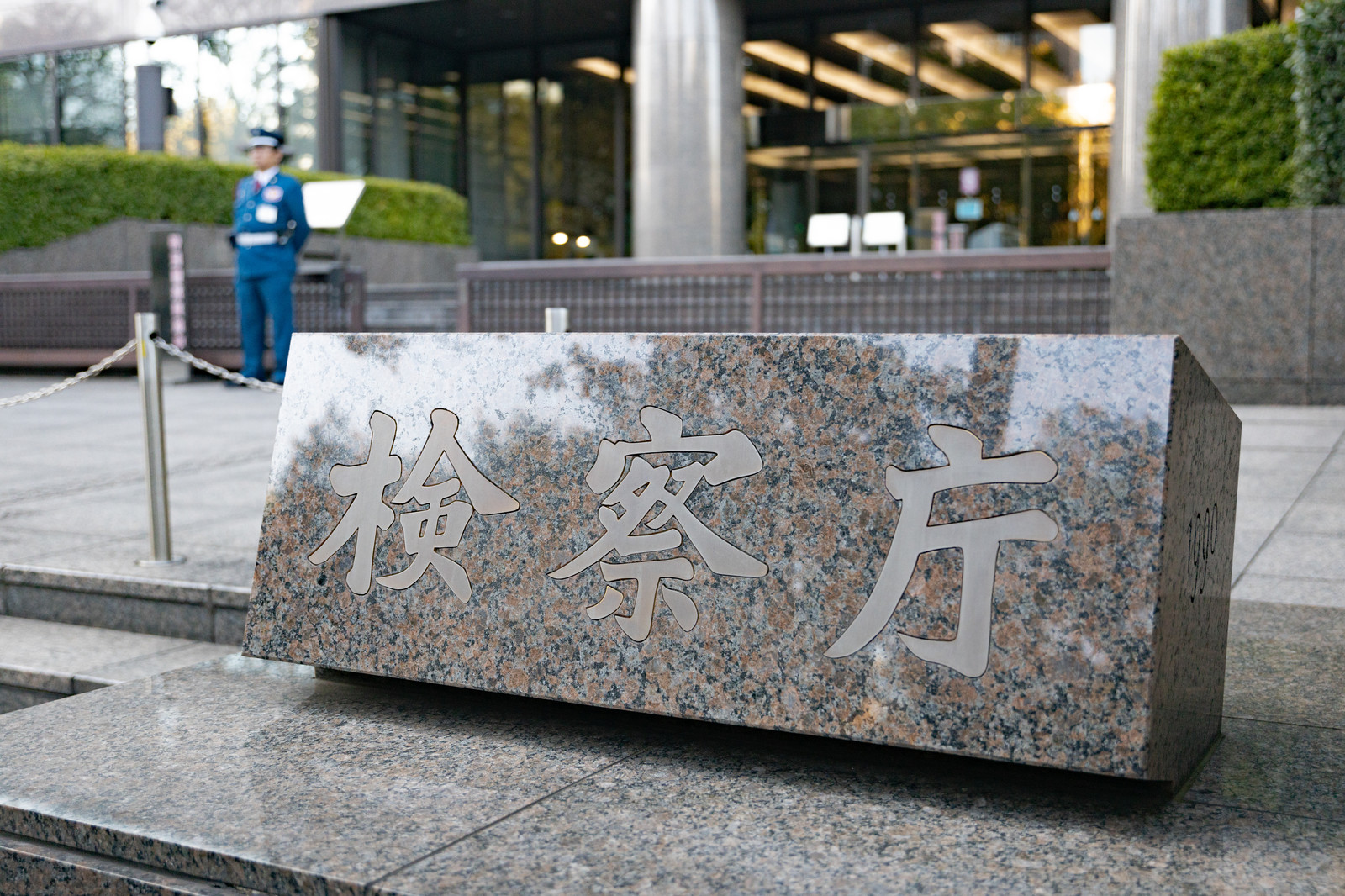同性パートナーは犯罪被害者給付金を受け取れないのか?
令和2年6月4日名古屋地裁判決(角谷昌毅 裁判長)の内容
令和2年6月4日名古屋地裁判決(角谷昌毅 裁判長)は、同性パートナーを殺害された者は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」といいます。)5条1項1号にいう「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)」に該当しないとして、犯罪被害者等給付金を支給しない愛知県公安委員会の裁定を是認しました。
なお、同判決は、「本件処分時点では」との留保を付けていますが、本件処分時点(愛知県公安委員会が原告に対して犯給法に基づく犯罪被害者等支給金を支給しない旨の裁定をした時点)とは、平成29年12月22日です。
割と最近の話ですね。
犯給法、犯罪被害者給付金とは?
犯給法というのは、犯罪被害者が受けた犯罪による経済的・心理的ダメージを早期に軽減するために一定の条件を満たす犯罪被害者や遺族に対して給付金を支給する旨を定めている法律です。
給付金の額は、障害の程度や被害者や遺族の収入、遺族の数等により変わりますので、死亡の場合の遺族給付金であっても数百万円〜約3000万円と幅があります。
遺族給付金についてのポイントは、給付対象者に「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」が含まれているという点です(犯給法5条1項1号)。
第五条 遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。一 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=355AC0000000036
争点:同性パートナーは「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」といえるか。
上記裁判例の原告(男性)は、平成26年12月22日当時、共同生活を継続していた男性(被害者)を、原告と交際していた別の男性(加害者)に殺害されました。
本件では原告が被害者と平成6年頃から交際するようになり、上記殺害事件が起きるまで共同生活を営んでいたことが認定されています。
ここでの争点は、原告が、被害者と「事実上婚姻関係と同様の事情にあった」といえるかどうかという点です。これは専ら原告と被害者が両方とも男性であったことから生じている争点であり、仮に原告と被害者のどちらか一方が男性でどちらか一方が女性であった場合には、問題なく「事実上婚姻関係と同様の事情にあった」と認定された事案であったと思われます(つまり、原告が加害者とも交際していたという事情はこの争点に影響を及ぼすものではなく裁判所の判断でも触れられていません。)。
これに対して、まず愛知県公安委員会は、原告は被害者と「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に当たらないとして犯罪被害者給付金の支払いをしないという裁定をしました。
上記裁判は、この裁定を不服とした原告が裁定を取り消すよう求めたものです(支給するよう求めるのではなく取り消すよう求めるのは法技術的な話なので気にする必要はありません。要するに取り消して支給しろということを求めている物です。)。
この裁判は、同性婚訴訟(法律上同性婚が認められていないことは憲法違反であるという裁判)が起こされてから1年3ヶ月以上経過した令和2年6月4日時点で、同性婚訴訟と類似した問題(要するに、同性パートナーを持つ人も、異性パートナーを持つ人と同様の法的保護を受けるべきではないのかという問題)について同性婚訴訟に先行して結論を示す形になりました。
この点について、原告は、①重婚的内縁や近親婚的内縁という法律上婚姻が禁止されている類型の内縁関係にあった者も「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当しうることは解釈として確立していることを指摘し、そうであれば法律上禁止されているわけではない同性婚的内縁関係も当然に「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当しうると主張しました。また、原告は、②渋谷区の同性パートナーシップ公証制度をはじめ、LGBTの権利に関する社会的な動きを指摘して、社会的にも同性パートナーでも「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」と認定されなければならないと主張したようですが、名古屋地裁(角谷昌毅 裁判長)が出した結論は、NOでした。
つまり、名古屋地裁(角谷昌毅 裁判長)は、同性パートナーを持つ人が、異性パートナーを持つ人と同様の法的保護を受けなければいけないとする理由はないと判断したわけです。
その理由として、裁判所は、①については、そもそも民法上の婚姻は男女を想定されて制定されており、重婚や近親婚については政策的に禁止されているに過ぎないのに対して同性婚は民法上想定されていない(ので同性パートナーを「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」と認定する理由にならない)としましたが、個人的には、この点はまあそうかなと思える判断です。
私が問題だと考えるのは、②の点についての裁判所の判断です。
名古屋地裁(角谷昌毅 裁判長)は、まず大前提として、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に当たるか否かは、社会通念によって判断されるとしました。そして、②のような社会的な動きを考慮しても、「本件処分当時においては、同性間の共同生活についての理解が社会一般に相当程度浸透し、差別や偏見の解消に向けた動きが進んでいるとは評価できるものの、同性間の共同生活を我が国における婚姻のあり方との関係でどのように位置付けるかについては、いまだ社会的な議論の途上にあり、本件処分当時の我が国において同性間の共同生活関係を婚姻関係と同視しうるという社会通念が形成されていたということはできないというほかない」と判断し、原告は被害者と「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に当たらないと結論しました。
令和2年6月4日名古屋地裁判決(角谷昌毅 裁判長)の問題点
私は、令和2年6月4日名古屋地裁判決(角谷昌毅 裁判長)の上記判断は憲法違反であると思います。既に、別コラム「認められるか、同性婚?」でも書きましたが、私は、同性婚を認めない現状は憲法14条の平等原則に違反しており違憲であると考えています。婚姻という制度において、同性愛者と異性愛者の扱いを異にする合理的理由がないからです。
ここで重要なのは、仮に社会の多数が許容していることであっても、それが人権侵害であり憲法違反であるということは十分にありうるということです。民主主義社会では、社会は原則として(選挙に参加する人たちの中での)マジョリティ(多数派)の利益に適うよう作られていきます。それ自体は民主主義を取る以上は当然であり、むしろ必要なことですが、マイノリティ(少数派)の権利に配慮することを意識しなければ、マイノリティの人権を侵してしまう危険があります。多数決によっても侵されない権利があり、その権利を守らなければならないという考え方であり、立憲民主主義とも言います。
立憲民主主義において重要な役割を担うのが裁判所です。立憲民主主義の下では、裁判所は、国会その他の権力機関から独立した機関として存在しており、多数決の原理によらない判断ができる国家機関として存在しているわけです。
だから、裁判所は、ある判断が正しいかどうかを判断するにあたっては、単純な社会通念によるのではなく、多数決によっても侵されてはならない権利にも十分に配慮した判断をする必要があります。
特に、法律というのものは極論全て社会通念に基づいて作られているわけですから、ある法律の規定自体がおかしいとか規定の解釈がおかしいという事案では、その規定や規定の解釈の正しさを判断する際に社会通念を持ち出してはいけないのです。社会通念に基づく法律解釈が誤っていると主張している人に対して、法律解釈が誤っているかどうかは社会通念で判断するというのでは、循環論法になるだけだからです。
社会通念が間違っていることがあるというのは、これまでの人類、いや日本に限って見ても多くの差別や偏見があったことからも理解できると思います。女性に選挙権が与えられないとか、一定の障害者に対して強制不妊術を施すなど、その当時の「社会通念」では当然とされていたことが「間違っている」ことは現代の我々から見れば明らかです。
これは、社会通念が変わったことで当時正しかったことが現在においては間違っていると言っているように見えるかもしれませんが、違います。その当時においても社会通念自体が間違えていたというべき例です。
「社会通念に基づく解釈は間違っている」と判断することができる機関があることは、民主主義社会で生きるマイノリティのセーフティネットとして非常に重要であり、その判断をする権能を与えられたのが他ならぬ裁判所なのです。
だから、「そんな法律解釈は間違っている」という訴えに対して、裁判所が「そんな法律解釈が間違っているかどうかは社会通念に従う」という前提を取るのは愚の骨頂というほかありません。多くの場面においては、法律解釈は社会通念に従って行えばいいのですが、こと「法律自体が間違っている」とか「法律の解釈が間違っている」という訴えがある場合に、その判断の拠り所を社会通念にするのでは、結論ありきで何も判断していないに等しいからです。
本件訴訟は、まさに、愛知県公安委員会の「法律の解釈が間違っている」という点が主張された事件です。ですから、これに対して、名古屋地裁判決(角谷昌毅 裁判長)が、その解釈が正しいかどうかは社会通念によるという前提をとった点は、非常に大きな問題なのです。
社会通念の捉え方を間違えているのではないかということよりも遥かに大きな問題だというべきです。
でも、社会通念の捉え方も間違えてない?
名古屋地裁判決(角谷昌毅 裁判長)の判断によれば、平成29年12月22日時点にの社会通念では、同性間の共同生活では、一方にとってもう一方が「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に当たることはないということになります。
前述の最大の問題点を置くとしても、その社会通念の捉え方が本当に正しいのかという点も疑問です。
同性間の共同生活について、「差別や偏見の解消に向けた動きが進んでいる」と認定しながら、法律婚をしていない異性間の共同生活について「事実上婚姻関係と同様の事情にあった」といえる場合があるのに、同性間の共同生活については「事実上婚姻関係と同様の事情にあった」といい得る場合はないというのは、まさに「差別や偏見の解消に向けた動き」のなかにある社会通念に反しているように思われます。
裁判所の判断枠組みの中で、原告が主張した同性婚の立法に向けた動きなど多くの社会的事実について触れられていることからすると、原告としては、本件処分時の社会通念においても、同性間の共同生活を「事実上婚姻関係と同様の事情にあった」といえると認定してもらうことを目標にしていたのかもしれません。
しかし、社会通念というのはかなり評価的なもので、ある種のマジックワードであり、裁判所に社会通念はこうだと言われてしまうと、判断材料を追加的に持ってくること以外に反論のしようがない面があります。
原告は控訴するようなので、控訴審が、名古屋地裁判決(角谷昌毅 裁判長)について、「社会通念の捉え方が間違っている」とするのか、「社会通念で判断するのが間違っている」とするのか、「何も間違っていない」とするのか、注目しています。