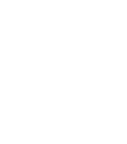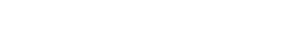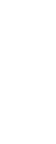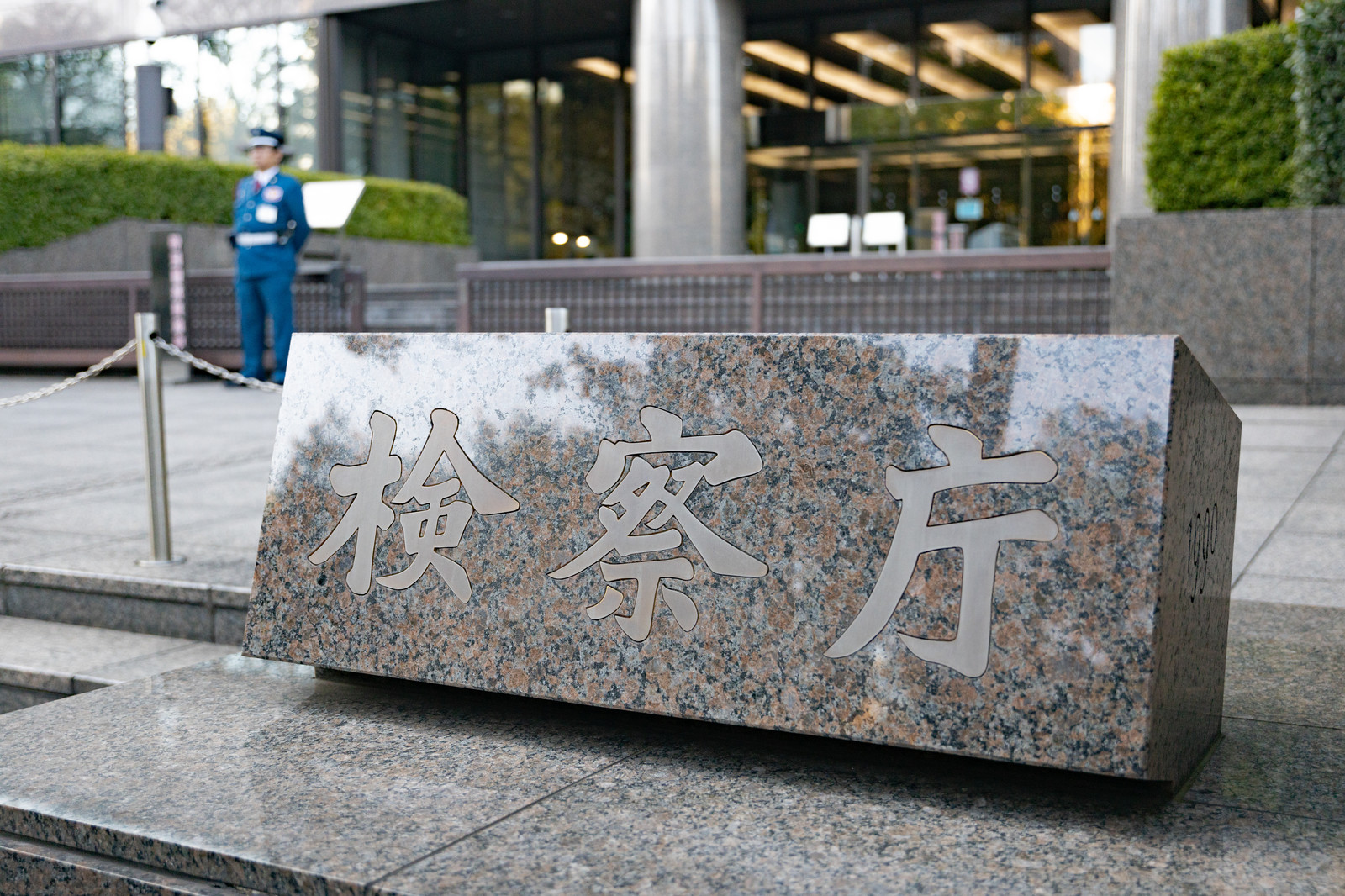大改正!ここが変わるよ相続法。

40年ぶりの大改正となる相続法
民法の重要な部分を占める相続法ですが,長年にわたりほとんど改正されてこなかった(非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする規定は違憲であるという平成25年9月4日の最高裁決定を受けて法改正されています。)分野ですが,平成最後の年にとうとう改正されることになりました。民法は債権法も大改正されて,どんどん現代に応じた法律に変化していっています。
なぜ改正するの?
相続法は,どうして改正されたのでしょうか?
上でも触れましたが,非嫡出子の法定相続分を2分の1とする民法の規定が違憲無効であると断じた最高裁決定を契機に,高齢化や社会経済情勢の変化にも対応する相続法改正が必要だという問題意識から,相続法の抜本的見直しが図られたものと言えます。
改正で,何がどう変わるの?
今回の相続法改正で変わるものとしては,大きく7つのテーマがあります。新設された規定もあれば,従来の判例法理を明文化したものなどもあります。
1 配偶者居住権
2 遺産分割
3 遺言制度
4 遺言執行者の権限
5 遺留分制度
6 相続の効力
7 相続人以外の寄与分
です。順に見ていきましょう。
1 配偶者居住権(1028条)
今回の改正の目玉ともいえるテーマです。
被相続人名義の建物に住んでいた配偶者が最も欲しい遺産は,普通はその住居です。ところが,従来の規定では,相続人間に争いがある場合,配偶者がその生活の本拠となる住居を手放さなければいけない状況にありました。
具体例でいうと,例えば,被相続人名義となっていた建物の時価が3000万円,現預金が2000万円が遺産であり,相続人が配偶者と子供一人だった場合,相続分は1:1となりますから,配偶者は建物を相続すると現預金は一切相続できないばかりか,500万円を子に支払わなければならないことになります。これが払えないとなると,建物を手放さざるを得なくなる可能性があったのです。
これが,配偶者居住権という概念を認めることで,配偶者は「配偶者居住権」を相続財産として相続し,法定相続分からその評価額を控除した分について相続することができます。具体的には,例えば上記例での配偶者居住権評価額が2000万円だった場合,配偶者は,住居に居住しながら500万円の相続財産を受け取れることになります。子は,配偶者居住権付の住居(評価額1000万円)と現預金1500万円を受領することができるわけです。
ただし,配偶者居住権は無償で原則終身居住し続けることができるという強力な権利ですから,相続が発生すれば直ちに認められるものではなく,一定の要件があります(当然ですが,配偶者であることと被相続人名義の建物に居住していることは前提です。)。配偶者居住権を取得する方法としては,遺言による方法,遺産分割による方法,家庭裁判所の審判による方法があります。また,当該建物が被相続人の単独所有でない場合には配偶者居住権は認められません。
また,配偶者居住権と類似の「配偶者短期居住権」も新設されました。これは,一定期間は配偶者が無償で相続財産である建物に居住できる権利であり,原則として遺産分割が確定する日か相続開始後6ヶ月のいずれか遅い日まで住み続けることができるというものです。実は,従来の相続法の中でも,最高裁は,類似の権利を認めていました(最判平成8年12月17日)が,これを解釈レベルではなく法律上の規定に昇格させたものが配偶者居住権です。
いずれも,被相続人名義の建物に住んでいる配偶者の生活を守る趣旨で新設された規定です。実務的には,配偶者居住権の評価方法などが課題になってくると思われます。
2 遺産分割
(1)特別受益の持戻し免除の意思表示の推定
今回の改正で遺産分割に関して,「特別受益の持戻し免除の意思表示の推定」,というものが盛り込まれました。いきなりわかりにくいですね。
特別受益というのは,相続人が生前に贈与していた財産も相続財産であるとみなして各相続人の具体的相続分を計算すべきであるという制度です。例えば,相続人が配偶者と子1人で,被相続人が生前に配偶者に対して建物(3000万円)を贈与されていた贈与しており,相続開始時に被相続人の財産が預貯金3000万円しかない場合,生前贈与された3000万円も相続財産として合計6000万円を相続財産とみなし(みなし相続財産),これを基準に法定相続分に応じて現実的な遺産分割を行うというものです。この場合,既に3000万円を受領した配偶者は現預金を相続することはできず,子が3000万円全額の現預金を相続することになります。
上記のように,生前贈与された財産を相続財産とすることを「特別受益の持戻し」というのですが,被相続人が「持戻ししなくて良い」(持戻し免除)という意思表示をしていた場合には,上記のような計算をする必要はなく,上記例では配偶者は3000万円の現預金について半分を相続することができます。かなりの違いですよね。ただ,そういうことを知らずに持戻し免除の意思表示をしていないケースも多数あり,従来の相続法の規定では,配偶者の保護が十分でないというのに答えたのが冒頭の「特別受益の持戻し免除の意思表示の推定」です。
これは,被相続人の配偶者への贈与であること,居住の用に供する建物又はその敷地であること,婚姻期間が20年以上である場合には上記推定が働くことにして配偶者の保護を図ったものです。ただし,あくまで推定なので,他の事情により覆されることがある点は注意です。
(2)特別受益は10年前まで
従来,特別受益は制限なく溯って持ち戻すことができると解釈されていましたが,紛争解決という意味や立証の実効性という意味において,合理性があるのか疑問視されていました。
そこで,新相続法では,特別受益の持ち戻し対象となる贈与を10年前までに制限されることになりました(1044条3項)。
(3)預貯金仮払い制度
従来,可分債権である預金債権は相続開始時に相続人に当然に分割承継されると解釈されており,遺産分割の対象にならないものと扱われていました(最判例昭和29年4月9日)。しかし,預金債権を遺産分割の対象とすることできめ細かい調整ができるようになるという要請もあり,最高裁は,預金債権が遺産分割の対象となることを認めました(最決平成28年12月19日)。
しかし,これにより,金融機関は,預金債権が相続人の誰に帰属するか確定するか,相続人全員の同意がない限り,預金を引き出させないという運用を強化しました。遺産分割の対象となるとすればさもありなんという運用です。
そうなると,被相続人の預金口座で生計を立てていた配偶者などは,突然生活の原資となる預金を凍結されてしまい生計を建てていくことができなくなるという事態がおきかねません。
そこで,新相続法は,一定額までは遺産分割前に預金を引き出せることとしました。具体的には,預金債権の額のうち法定相続分の3分の1(ただし上限150万円)までであれば,遺産分割前に引き出すことができます。
関連して,従来厳格な要件が設定されていた遺産の仮分割(家事事件手続法200条2項)について,相続人の生活費に支弁するために必要のある場合に預貯金債権を仮分割できるという制度が新設されました(同法200条3項)。
(4)遺産分割前の遺産処分の取扱い
従来の規定では,遺産分割前に使い込みされてしまった遺産については,遺産分割の対象とならず(!),不当利得の問題として処理されています。一般市民の方からすれば,この理屈はどうでもいいと思うのですが,実際的な問題として遺産分割とは別に不当利得返還訴訟を提起しなければいけないという不都合がありました。
この場合でも相続人全員が同意すれば処分した財産を遺産分割の対象とすることもできると解釈されていたのですが,使い込みをした相続人の一人が実際に同意することはまず考えにくいですよね。この不都合に対応するため,共同相続人によって遺産が処分された場合には,その相続人の同意がなくても他の相続人の同意により処分された遺産について遺産分割の対象とすることができるようになりました(906条の2 2項)。
3 遺言制度
(1)自筆証書遺言書の保管制度
従来の遺言には,自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言があり,実際に使われているのはほぼ自筆証書遺言と公正証書遺言です(秘密証書遺言の利用件数は年間100件程度だそうです。)。公正証書遺言であれば,遺言の原本は公証役場に保管され法令で定められた期間は破棄されることもありませんし,相続人が被相続人が公正証書遺言を作成していたかを検索することもできます。
これに対し,自筆証書遺言は,遺言者自らが保管しておかなければならず紛失や滅失のリスクがある上,そもそも死後発見されないとか,発見されたとしても破棄されてしまうなどのリスクがあります。
そこで,今回の大改正にあたり,新相続法は「法務局における遺言書の保管等に関する法律」を制定して,法務局が自筆証書遺言の保管をしてくれる制度を新設しました。法務局は当該遺言書の原本を保管するほかデータ化して管理し,遺言者の死亡後に相続人等の一定の者(関係相続人等)からの請求により遺言書情報証明書を発行することになります。また,関係相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり閲覧をした場合には,遺言書保管官から遺言書の相続人,受遺者,遺言執行者に通知が行きます。
このように,自筆証書遺言であっても,いわば「検索」ができるようになり,遺言書の存在が分からないまま相続が完結してしまうことを防げるのが,大きな利点です。是非とも活用が進むことを期待します。
(2)自筆証書遺言の有効要件の緩和
従来,自筆証書遺言が有効であるためには,全文の自書が必要とされており,本文をワープロ打ちして署名押印したものは無効とされていました。相続財産があまりない場合にはいいのですが,相続財産が多数あり財産目録を用意しなければいけないような場合に,その財産目録まで自書しなければならないので大変な負担でした。まあ,それなら公正証書遺言作ればいいじゃん,とも思うのですが,やはり自筆証書遺言の簡易性に一定の需要はあるのでしょう,新相続法は,自筆証書遺言の中で相続財産の目録については自書でなくても良いということにして有効要件を緩和しました(968条2項)。
ただし,その財産目録の全てに署名押印が必要である点は注意してください。
4 遺言執行者の権限
(1)相続人の代理人ではない
遺言執行者というのは,従来の相続法の中でも重要な職責を負う立場であることは確かなのですが,その権限や権能がいまいち不明確であるという欠点がありました。旧法では遺言執行者は「相続人の代理人」とされていたのですが,遺言の内容によっては相続人の利益に反する遺言を執行しなければならない立場にあり,「相続人の代理人」というのはかなりの違和感がありました。
新相続法では,遺言執行者は,「遺言の内容を実現するため・・・遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされ(1012条1項),「相続人の代理人」とした規定も削除されました。
(2)復任可能
また,従来,遺言執行者はやむを得ない事由がなければ第三者にその任務を負わせることができないとされていましたが,必ずしも適切な者が遺言執行者として指定されていない場合も多々ありました。
そこで,新相続法は,遺言者が別段の意思を表示しない限り,自己の責任により第三者に任務を負わせることができるとされました(1016条1項)。
(3)特定財産承継遺言でも権能あり
実務上,遺言執行者の権能が問題となるケースとして,「相続させる」旨の遺言があった場合があげられます。例えば,「相続人Aに甲不動産を相続させる。相続人Bに乙預貯金を相続させる。」という内容の相続の場合,相続人Aは甲不動産について単独で所有権移転の登記をすることができるため,遺言執行者が登記移転の義務を負うことはないとされていました(最判平成7年1月24日)。また,相続人Bも乙預貯金について単独で払い戻し請求をすることができるため,遺言執行者には乙預貯金の払い戻しの権利義務がないともいえそうです。
新相続法では,上記のような特定財産承継遺言がある場合に,遺言執行者は対抗要件具備に必要な行為(1014条2項)や,預貯金の払い戻し請求や解約申し入れ(1014条3項)権限があるということが明確化されました。これによって無用な問答,紛争を防ぐことができるようになり,よりスムーズな遺言執行が可能になることが期待できます。
(4)遺言執行者がいる場合の相続人の行為の効力
従来,遺言執行者がいる場合,相続人が相続財産を処分しても,それは絶対的に無効であると理解されていました。
しかし,遺言があるのか,その遺言で遺言執行者が指定されているのかなどは第三者には分からないのが普通であり,絶対的に無効としてしまうと取引の安全を害することになります。
そこで,新相続法では,善意の第三者との関係では遺言執行者が指定されていることだけでは対抗できないこととされました(1013条2項)。
なお,相続人の債権者(相続債権者を含む)が相続財産について権利行使することは遺言執行者がいても妨げられないことも明らかにされました(1013条3項)。
5 遺留分
従来,遺留分減殺請求がされると,相続財産全てが受遺者と遺留分減殺請求者の共有になると解釈されていました。しかし,このような理解では,共有状態の不動産の売却が困難になるなど現実的には様々な不都合があると指摘されていました。
そもそも遺留分減殺請求がされるような関係性では,対立構造になっているわけで,あえて対立構造にある当事者の「共有」にするという理屈に合理性があるとは思えません。当事者としてもどちらも共有状態を望むことは少なく,実際的には価額弁償の方法で対応することがほとんどです。
そこで,新相続法は,遺留分減殺請求権は,「遺留分侵害額請求権」という債権的請求権であるとされました。従来の,価額弁償の方法に統一されたというわけですね。大きな理論的変革です。
6 相続の効力
(1)対抗要件としての登記
従来,例えば遺言により法定相続分を超える相続分の指定がされた場合の不動産の権利取得について,判例は,その指定を受けた相続人は登記なくしてその権利を第三者に対抗できるとしていました。また,「相続させる」旨の遺言がある場合も,遺産分割方法の指定とした上で法定相続分を超える権利を取得した相続人は,やはりその権利を登記がなくても第三者に対抗できると解釈されていました(最判平成14年6月10日)。
しかし,遺言の有無や内容は第三者には分からないのが普通であり,上記のような理解では取引の安全を害することになるのではないかという問題意識がありました。
そこで,新相続法は,相続による権利の承継について法定相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないと定めました(899条の2 1項)。
これは取引の安全を強化したものといえますが,相続人側から見ると,今後はこれまで以上に早期の対抗要件具備が重要となることを意味します。
(2)債権の対抗要件
債権譲渡の対抗要件として代表的なものは元の債権者から債務者への譲渡通知です。そこで,債権が遺贈で譲渡された場合も,遺贈義務者から債務者に対して通知がなされなければ,受遺者は遺贈による債権取得を債務者に対抗できないとされています(最判昭和49年4月26日)。
では,相続分の指定や「相続させる」旨の遺言で債権を相続する場合や,遺産分割で預貯金債権を相続する場合に,上記のような対抗要件は必要でしょうか?
この点について,新相続法は,法定相続分を超えて債権を承継した相続人が承継原因となる遺言や遺産分割の内容を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは,共同相続人全員が通知をしたものとみなして債務者に対応することができることとしました(899条の2 2項)。
7 相続人以外の寄与分
従来,寄与分が認められうのは相続人に限定されていました。しかし,実際には相続人でない者(例えば相続人の配偶者や子など)が懸命に被相続人の療養看護を行なっているようなケースは多く,このような場合に,これらの者の行為を全く評価しないのでは公平を害するのではないかという問題が指摘されていました。
そこで,新相続法は,「特別の寄与」という項目を作り,相続人の親族が無償で被相続人に対して療養看護を行なっていた場合には,その親族は,相続開始後に相続人に対して「特別寄与料」を請求できることにしました(1050条)。
実務的には,この特別寄与料の金額が今後の課題となっていくでしょう。